電車のつり革はどうしてあんなにも動いて不安定なのか?
こんにちは、hatpoppoです。
今度、大学院生になるのですが、大学までの通学には電車とバスを利用しています。
そこで時々、イスに座れずにつり革を支えに立って電車やバスに乗っています。
これは皆さん経験したことがありますよね。
車内で立っている時、僕はこう思いました。
「つり革って全然支えになっていないじゃないか!」
「つり革がこんなにも動いてしまっては、体が全然安定しなくて不便だ!!」
こんなように、皆さんもイライラを感じたことはないでしょうか?
今回の記事では、この
「つり革は、体を支えるためのものなのに、なぜあんなにも動くものが使われているのか」
について考えていきたいと思います。
早速ですが、今回取り上げた問題の解決に重要な点は、「体のバランスを取りやすくする」ということです。
そこで体のバランスが崩れる1番の原因は、支えとなるつり革が大きく動いてしまうこと。
つまり、支えとなるもの自体が、動かず固定されたものであれば良いと考えられると思います。
そこで僕はこんな感じのイメージのつり革の代わりとなるものがあれば良いなあと思えました。

こんな感じで、金属パイプのように硬く固定された支えならば、電車やバスの揺れによる体のバランスの大きな崩れを少なくできるのではないでしょうか。
では逆になぜ、現在利用されているつり革は、あんなにも動いてしまう設計になっているのか。
それに対していくつか仮説を立ててみました。
仮説はこんな感じです。
- 雑菌繁殖抑制のためにつり革を取り替えることがある
- つり革の取り替えコストを抑えるための材質選択によって柔らかい材質が選ばれてしまった
- 体のバランスを崩した場合に頭に当たっても問題ない材質にする必要があったから
これらの仮説を1つずつ検証していきたいと思います。
まず、1つ目の「雑菌繁殖抑制のためにつり革を取り替えることがある」について。
ネットで「つり革 交換」や「つり革 取り替え」と検索してみたのですが、関係する内容は見つかりませんでした。
しかし、つり革は抗菌仕様となっており、さらに定期的に掃除されているらしいです。
電車のつり革に触りたくない!ちゃんと除菌や抗菌はされているの?
汗が気になるこの時期! 電車のつり革の掃除は10日1回ってホント!? 東京メトロに直撃!
よって、つり革を交換しているという仮説は成り立たず、仮説1,2は共に間違った仮説であったことが分かりました。
まぁ、少し考えてみれば、たくさんある電車の中にさらにたくさんあるつり革を定期的に取り替えなんてしていたら、コストが膨大になってしまって非効率極まりないですよね。
ということで次の仮説の「体のバランスを崩した場合に頭に当たっても問題ない材質にする必要があったから」について。
これについては気になる記事を見つけました。
要約すると、つり革を設置する位置を決めるのは難しいということ。
これはつり革が高い位置にあると背が低い人にとって使いずらいが、逆につり革が低い位置にあると背が高い人の頭などにぶつかりやすく危険ということです。
この問題に対して、ここでは高さを工夫するのか、それとも痛くない材質にするかを検討するらしいです。
これについては、興味深い点があって、読んでいて面白かったのですが、仮説3に対してはあまり関係がない内容でした。
ここから、安全を考えた材質の検討という案はあるものの、体のバランスを支えるための方法という視点からの考えはないのではないかと思いました。
そのため、この仮説3に対しては推測をするということにします。
仮説3に対して、硬くて危険なものがつり革の代わりである場合、背の高い人の頭にぶつかったりして大変危険だから。ということでしょうか。
まとめ
電車やバスの中でお世話になるつり革。
体のバランスが崩れやすい車内の中で、バランスを安定させるために必要なものですよね。
しかし、体のバランスの安定のためなのに、どうしてあんなにもつり革は動くのでしょうか。
金属などの硬く固定されたものなら安定感はもっと高くなるはずでは?ということで色々と考えていきました。
最後に
今回はこんなように、ただただ気になったので調べながら考えてみましたという感じの記事でした。
日頃から生活していくと調べるのが後になって知らないことが増えていき、なぜなんだという気持ち悪さだけが残ってしまっていました。
ですので今後は、こんな感じの記事を書くことで分かった気になり、気持ち悪さをなくすというのを目的に色々調べていきたいと思います。
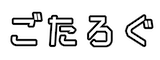







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません